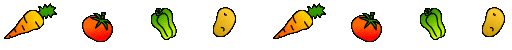
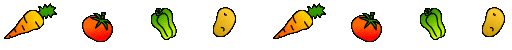
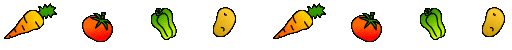 |
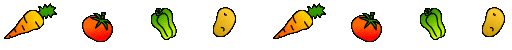 |
![]()
| NO,41 小さな弱い人を守る | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
昨年十二月九日付けの本紙「読者テレホン」欄のトップに、高知市の主婦の方からの「いじめ後遺症に苦しむ」という声が掲載された。郡部の狭い地域の中で、保育所の時からいじめを受け続け、頼みの先生がいじめる側に加わることもあり、人間を誰も信頼できないままに、心も体もガタガタになり、今も後遺症に苦しんでいる娘さんを持つ親の、無念の思いが切々と語られていた。「県教育長は田舎のこんな実態をご存じでしょうか」という問いかけもあった。早くお答えしたいと思ったが、どうお答えすべきか、思いあぐねていた。 いじめをどう解決するか、どう未然に防ぐか、傷ついた心や体をどう癒すか、失われた命をどう償うか、残念ながらこの国には誰も、それに明確に答えることができる人はいない。自分なりの思いをつづってお答えに代えるほかない。 ぼくも四国山脈の山深い田舎で生まれ、定時制高校の三年生まで、十七年間を過ごした。どん底の貧しさの中で、田舎が見かけほど、のどかで平和な世界ではないことは骨身に沁みて承知している。狭い地域では、その家の経済力や本人の体力、腕力で、子どもの人間関係は完全に固定化、序列化される。その序列は十数年間、びくとも動かなかった。ぼくはその中で、あらん限りの知恵をしぼって生きのびた。 宿業だろうか、ぼくの子ども達も、「読者テレホン」の娘さんとほぼ同じ経過をたどっている。ぼくは我が子を守ってやることができなかった。我が子は「読者テレホン」の被害者の方と相前後する年齢になり、同じようにいじめの後遺症、深い心の傷に苦しんでいる。 平成十二年四月一日、はからずも教育に携わる職に就いたぼくの最初の仕事は、新採用教職員に辞令をお渡しすることだった。その時、短いあいさつをした。人前で極端にあがるくせのあるぼくは、ふるえるか細い声で、「子どもの命と尊厳を守る」「いつも弱い子どもの味方になる」ということを若い先生方にお願いした。以来このことは、先生方にお話をする機会があるごとに語り続けている。ささやかながら、手応えも感じている。 いじめは、学校を責めることだけでは解決しない。生徒に対する管理や懲戒を強めることでも、おそらく解決しない。 いじめは、どの学校のどの教室でも起り得る。その原因は、学校にも家庭にも、いじめや格差、非人間的な競争を許容している社会全体にもある。 いじめは、いじめられている被害者が声をあげることができないため発見が難しく、仮に発見できても、被害者の心の傷のケア、加害者や傍観者の適切な指導による更生が容易ではない。いじめは犯罪である。けんかと違い、謝罪や和解という形の解決が難しい。 様々ないじめのケースと格闘しながらぼくがたどり着いた結論は、いじめの起きない学校、学級づくりに取組むことが何より大切だ、それは学力問題をはじめ、不登校、非行、中途退学など、深刻な教育課題全体を根本的に解決する道に通ずる、ということだった。 そのための具体的な方法論は、土佐の教育改革を検証する中で明らかになっている。
こうして、子ども達と教職員、保護者や地域の人々の間に信頼関係を築くことができれば、子ども達の心を温かいものに変えていくことができる。学校を温かい居場所にすることができる。ここから、家庭や地域社会の教育力の向上にアプローチする道も開けるだろう。教育環境は日々厳しさを増しているが、それをもう一度、子ども達にとってよりよいものに変えていく展望を、ここから開きたい。
ぼくはワイシャツの胸ポケットに手作りのお守りを入れている。事務局に勤めておられた若い臨時職員の方が退職される時、お菓子と一緒に小さなメモをくださった。「小さくて弱い人達を守ってあげてください」と書かれていた。短い期間一緒に仕事をさせていただいただけなのに、この方が、ぼくのやろうとしている仕事の本質を理解してくれていたことが嬉しかった。 |
||||||||||||||||
     |
||||||||||||||||