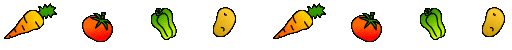
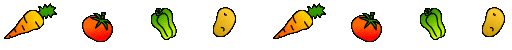
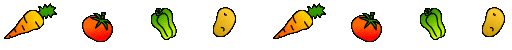 |
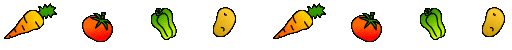 |
![]()
| NO,42君看(み)よ双眼のいろ | ||
|---|---|---|
|
初夏の山畑は、今年も夏草の海。草を一メートル四方ほど刈り取って耕し、鶏糞を元肥に苗を植えた。刈谷先生にいただいたワラを根元に敷いた。ぼくがしてあげられることは、これだけ。後は自分の力で生きのびるんだよ。テツカブトとゴーヤの苗に言い聞かせた。 トイレを磨いて心を磨くという奉仕活動に、全国各地で取組んでおられるイエローハットの鍵山秀三郎さんが、フタガミの社長さんに託して、相田みつをさんの詩集を届けてくださった。私ごとき者へのこんなお心配り、もったいないことである。「五十ページの「憂い」にご注目のほどを」という添え書きまでしてくださっていた。 <むかしの人の詩にありました 君看よ双眼のいろ 語らざれば憂い無きに似たり 憂いがないのではありません 悲しみがないのでもありません 語らないだけなんです 語れないほどふかい憂いだからです 語れないほど重い悲しみだからです> 教育をめぐる環境は、様々な意味で日々厳しさを増している。子ども達は家庭で育ち、学校で育ち、まちやむら、地域社会の中で育つ。 経済的格差の広がる社会の中で、多くの子ども達の家庭の生活基盤が脅かされている。子ども達を温かく見守るべき地域社会の連帯意識も、急速に失われつつある。学校はそれらの歪みを一身に背負って、悲鳴をあげている。 多くの保護者や教職員の方々から、たくさんの訴えや悩み事相談をいただく。年々その数が増える背景には、ぼくが無謀にも、そのひとつひとつに応えようとしていることのほかに、こういう教育環境の厳しさがあるだろう。 解決できる問題もある。どんなにもがいても、解決できない訴えもある。感謝していただけることもある。共通理解ができ、互いに励まし合うことで収束するケースもある。教育への信頼をつなぎとめることができない事例もある。その時は、双方に重い悲しみ、憾(うら)みが残る。 過日、来高されてお会いする機会ができた時、鍵山さんに、ぼくは唐突に自分の「憂い」を語った。背負って、背負いきれずによろめいている重い「悲しみ」をぶしつけに語った。鍵山さんは、慈愛に満ちた表情で耳を傾けてくださった。そして、そのお答えを、この詩で返してくださったのである。詩は続く。 <澄んだ眼の底にある ふかい憂いのわかる人間になろう 重いかなしみの見える眼を持とう 君看よ双眼のいろ 語らざれば憂い無きに似たり> ぼくにできることも、できないこともある。偽善、無能、というそしりを恐れず、悲しみの見えないことを恐れて、ひとつひとつの問いかけに精一杯応えて行こう。 鍵山さん、ありがとうございます。 |
||
     |
||